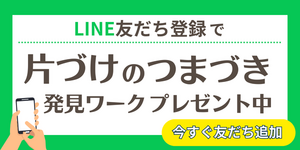「捨てる?捨てない?」迷いを断つ!プロが使う【人生が変わる4つの問い】と判断基準
2025/11/10
片づけ作業の中で、誰もが立ち止まるのが「迷うモノ」との対峙です。
「いつか使うかも」「高かったから」「思い出が詰まっているから」——捨てることにブレーキをかける理由探しをしているモノは、あなたの家の中にありませんか?
実は、この「迷うモノ」への対応こそが、片づけ成功の鍵を握っています。
捨てられない理由探しの罠
1. 過去の後悔に支配されていませんか?
片づけに苦手意識がある方に「あるある」なのが、「過去に捨てて後悔したから、また必要になって買い直したくない」という心理。
この記憶がトラウマとなり、家には「いつか使うかも」グッズがどんどん増えていきます。
もちろん、「絶対いる」と自信を持って言える物は、あなたにとって必要なモノです。しかし、「迷うもの」や「捨てない理由探し」をしているモノは、残念ながら今、あなたにとって必要でない可能性が高いのです。
2. 普段の暮らしを犠牲にしていませんか?
使うモノは全部表に出しっぱなし
使わない「かもグッズ」は収納にぎゅうぎゅう詰め
その様子を、あなたは心から望んでいますか?
「いつか使うかも」というモノに大切な日常生活のスペースを圧迫され、子ども部屋が作れない、勉強に集中できない、そんな環境になっていませんか?
迷いを断ち切る!自分に問いかける【プロの問いかけ4選】
モノと向き合い、判断に迷ったとき、立ち止まって自分自身に問いかけてみましょう。冷静な判断を促す、プロが使う4つの質問です。
「過去に買いなおしたモノの損失額」は、何円でしたか?
その金額と、モノを**「しまい続けるスペースのコスト(家賃・時間)」**を比べてどうでしょうか?
「他のモノでは本当に代用できませんか?」
代用できるなら、それは手放しても困らないモノです。
最後に手入れをしたのはいつですか?
手入れを続け、適切に使える状態を維持できていましたか?
「今と未来」を犠牲にしてまで、心から大切にしていますか?
ふと思い出して懐かしむことは素晴らしいですが、本当に全部必要でしょうか?若かったあの頃のモノを全部手放せとは言いません。ただ、限られた空間の中で優先順位をつけることが、豊かな生活には不可欠です。
大人の姿勢が子どもへの「片づけ教育」になる
私たち大人は、限られた空間と時間の中で、何が大切かを優先順位を決めて折り合いをつける必要があります。その姿を家庭内で見せることが、子どもにとっての片づけ教育の柱になります。
なぜなら、令和の日本では、消費や購買の仕組みが本当に多様化しているからです。
「これを買えば豊かになる」「素敵な部屋になる」「痩せられそう」「偏差値があがるかも」— 夢を抱くことは素敵ですが、それらは「買うだけ」ではなく、あなたの努力も付随してこそではありませんか?
使いこなせなかった便利グッズやダイエットグッズ、一度も開いていない参考書。「買うだけで満足」はもう終わりにしましょう。
本当に大切にしたい価値観を、あなたの家のなかから見つけること。それも私がお伝えしたい整理収納の大切なことのひとつです。
あなたの大切にしたいこと、ぜひ私に教えてくださいませんか?
「かもグッズ」に支配された暮らしから卒業し、今と未来が輝く快適な空間を一緒に作りましょう。
無料相談だけでも構いません、お気軽に聞かせてくださいね。
▼あなたの大切にしたい価値観を見つけるお手伝いをします▼
この記事を書いたひと
お母さんに「花丸!」とテーマに 大阪・兵庫の北摂地域を中心に訪問片づけサービスを提供しています
訪問片づけの詳細はこちらからご覧ください
-
 小4娘が大人と同じ「整理収納準1級」に挑戦!親子で学ぶ難しさと、得られた一生モノの力。
今日は1月7日。七草粥で胃を休めつつ、少しずつ「いつもの日常」のリズムを整えている頃でしょうか。昨日は中1の息
小4娘が大人と同じ「整理収納準1級」に挑戦!親子で学ぶ難しさと、得られた一生モノの力。
今日は1月7日。七草粥で胃を休めつつ、少しずつ「いつもの日常」のリズムを整えている頃でしょうか。昨日は中1の息
-
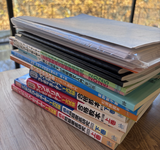 整理収納のその先へ。私が今、インテリアを学び続ける理由。
1週間、わが家の収納や子育てのリアルをお伝えしてきました。整理収納を語る上で、切っても切り離せないのが「機能性
整理収納のその先へ。私が今、インテリアを学び続ける理由。
1週間、わが家の収納や子育てのリアルをお伝えしてきました。整理収納を語る上で、切っても切り離せないのが「機能性
-
 脳内のメモリを節約せよ!片づけのプロの私が「アレクサ」に家事を丸投げする理由。
100日ブログを始めて、今日で9日目。昨日のブログの最後で、「私が全力で頼っている相棒」のお話をしました。「整
脳内のメモリを節約せよ!片づけのプロの私が「アレクサ」に家事を丸投げする理由。
100日ブログを始めて、今日で9日目。昨日のブログの最後で、「私が全力で頼っている相棒」のお話をしました。「整
-
 【10日目の感謝】あなたの「これ、どうしたら?」を、私に解決させてください!
1月1日からスタートしたこの「100日ブログ」。おかげさまで、本日10日目の節目を迎えることができました!三日
【10日目の感謝】あなたの「これ、どうしたら?」を、私に解決させてください!
1月1日からスタートしたこの「100日ブログ」。おかげさまで、本日10日目の節目を迎えることができました!三日
-
 書類の山に魔法はない。2026年の今、私たちが「やるしかない」現実と、その先の光。
100日ブログ、12日目。今日は、きれいごと抜きで、でも愛を込めて「書類」の話をします。紙1枚は、軽くて大した
書類の山に魔法はない。2026年の今、私たちが「やるしかない」現実と、その先の光。
100日ブログ、12日目。今日は、きれいごと抜きで、でも愛を込めて「書類」の話をします。紙1枚は、軽くて大した