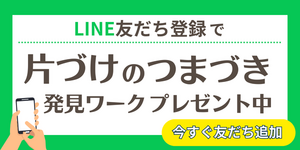ここまで包み隠さず内容を提示してくれるセミナーはない!!【家庭科の授業体験シェア会】
2024/09/13
小学5年生の家庭科「整理・整とん」の授業についてまるっとシェアする 家庭科の授業体験シェア会を開催しました!
大阪・豊能町の整理収納アドバイザーのひがしよしみです。
第4回目の開催となる「家庭科の授業体験シェア会」を終えました。
今年の1月からはじまったこのシェア会も4回目。参加者さんも50名近くになってきました!
なかには、
「初回から気になっていたんです!」
「見つけた時には前回満席になっていて、やっと参加できました!」
「初回から気になっていたんです!」
「見つけた時には前回満席になっていて、やっと参加できました!」
と開催を心待ちにしてくださっている方も増えてきました。
なんと、嬉しい!
さらには、
アドバイザーのお友達からの口コミでご参加いただいた方も。
プロ向けのシェア会だからこそ、同業の方がおすすめしてくださるなんてありがたいです。
で、何が学べるの?
さて、片づけのプロとして活動しているあなたが、ひょんなことから
地域の小学校の家庭科の授業「整理・整とん」単元のゲストティーチャーをつとめることになったとき、
何から準備をはじめて、どんな授業をおこないますか?
はい、ちょっと想像してみてください。
あなたが想像した授業は45分の1コマ?
それとも2コマ?3コマでしたか?
それとも2コマ?3コマでしたか?
実は、授業時間も学校によって異なることはザラです。
しかも、
授業依頼を受けて1か月後に授業を実施することもあります。
授業依頼を受けて1か月後に授業を実施することもあります。
どうでしょうか、そんな状況で「整理・整とん」の授業を安心して行えそうですか?
2023年に初めて「整理・整とん」の授業を私が実施したときには、1か月で授業の準備をすべて自分ひとりで行いました。
これでいいのかな?と手探り状態でしたが、やるしかない!と覚悟をきめてなんとか授業を終えて、振り返ったときにこう思ったんです。
「小学校で授業をしました!」という片づけのプロの発信はあるけれど、
授業の作り方や、すすめかた、依頼をどうやっていただくのか、その経緯は誰も教えてくれない……。
一生懸命つくり上げた授業は財産です。
だから、そう簡単には公開はしてくれません。
だから、そう簡単には公開はしてくれません。
そりゃそうですよね。試行錯誤のうえつくりあげたノウハウは宝物なんですから。
その一方で、
小学生に片づけのプロが知識や経験の引き出しをフル活用して、「整理・整とん」を伝えることは、とーーーっても価値があるんですよ。
「片づけめんどくさいし…」と授業のはじめに言っていた児童が
「このお道具箱見て!めっちゃきれいになった!」と目を輝かせて話しかけてくれるのは、
片づけのプロにとって何物にも代えがたい喜びです。
「片づけって楽しいかも」そう思える子ども達がひとりでも増えてほしいと心から願っていますし、
この喜びを多くの片づけのプロに実感してほしいから…
この喜びを多くの片づけのプロに実感してほしいから…
- 授業依頼をいただいた経緯
- 学校とのやりとり
- 授業の準備期間、準備物
- 実際の授業の様子
- 気づきや改善点
まるっと全部お伝えしています。
だって、私ひとりじゃ日本中の子ども達には伝えきれませんからね。
片づけのプロが手を取り合って授業を行えばより多くの子ども達に伝えられる!
そう願ってお届けした、4回目のシェア会の参加者さんからのお声の一部をご紹介します。
そう願ってお届けした、4回目のシェア会の参加者さんからのお声の一部をご紹介します。
参加者さんのお声
-

よくよく考えてもこのように具体的に最初から最後まで教えてくれるセミナーって他になかったような気がします。講師の勉強のセミナーでもここまで包み隠さず内容を提示してくれるセミナーはない!!(笑)
大御所の先生でもやらないようなことをやってくださり、大変感謝です。
-

同じ家庭科の授業でも進め方も内容も違ってメモでいっぱいになりました。日頃の先生方の大変さも改めて実感しました。聴けば聴くほど不安にもなりましたが、きっと大きな自信になるし児童の皆さんも貴重な経験になるしプラスになることばかりだと思いました。
今のタイミングで参加できてよかった。
-

みなさんそれぞれの内容をお聞きすることができたので、いろんなことを想定することができました。
ここがよかった、次はこうしようと思うなど、実際行ったことのある方の貴重な意見は、大変リアルでよかったです!
-

最初のアプローチから実際に使ったものまで、そこまで見せていいの??そこまでシェアしてくれるの??というくらい何でもシェアしてもらって、頭のなかでイメージが湧きまくりました!!
こんなに嬉しいお声が続々届いています!貴重なお時間をさいてご参加くださり、またアンケートにご協力くださり、本当にありがとうございます。
初回開催から50名近くの方にご参加いただき、授業を実施された方、授業の実施が決まった方、来るべきタイミングに備えて準備を始められた方など、本当にたくさんの「その後のご報告」もお寄せいただいています。
為になったなー!で終わりでなく、どんどん行動されている皆さんが続々といらしていて、
「家庭科の授業体験シェア会」を企画して本当によかった!と思います。
整理収納業界は年末に向けての繁忙期に入るため、次回の開催は来年2025年を予定しています。
私もチャレンジしてみたいな!と思われた方はぜひ、今後のお知らせをチェックしておいてくださいね
関連エントリー
-
 小4娘が大人と同じ「整理収納準1級」に挑戦!親子で学ぶ難しさと、得られた一生モノの力。
今日は1月7日。七草粥で胃を休めつつ、少しずつ「いつもの日常」のリズムを整えている頃でしょうか。昨日は中1の息
小4娘が大人と同じ「整理収納準1級」に挑戦!親子で学ぶ難しさと、得られた一生モノの力。
今日は1月7日。七草粥で胃を休めつつ、少しずつ「いつもの日常」のリズムを整えている頃でしょうか。昨日は中1の息
-
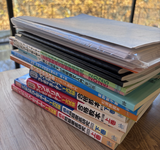 整理収納のその先へ。私が今、インテリアを学び続ける理由。
1週間、わが家の収納や子育てのリアルをお伝えしてきました。整理収納を語る上で、切っても切り離せないのが「機能性
整理収納のその先へ。私が今、インテリアを学び続ける理由。
1週間、わが家の収納や子育てのリアルをお伝えしてきました。整理収納を語る上で、切っても切り離せないのが「機能性
-
 脳内のメモリを節約せよ!片づけのプロの私が「アレクサ」に家事を丸投げする理由。
100日ブログを始めて、今日で9日目。昨日のブログの最後で、「私が全力で頼っている相棒」のお話をしました。「整
脳内のメモリを節約せよ!片づけのプロの私が「アレクサ」に家事を丸投げする理由。
100日ブログを始めて、今日で9日目。昨日のブログの最後で、「私が全力で頼っている相棒」のお話をしました。「整
-
 【10日目の感謝】あなたの「これ、どうしたら?」を、私に解決させてください!
1月1日からスタートしたこの「100日ブログ」。おかげさまで、本日10日目の節目を迎えることができました!三日
【10日目の感謝】あなたの「これ、どうしたら?」を、私に解決させてください!
1月1日からスタートしたこの「100日ブログ」。おかげさまで、本日10日目の節目を迎えることができました!三日
-
 書類の山に魔法はない。2026年の今、私たちが「やるしかない」現実と、その先の光。
100日ブログ、12日目。今日は、きれいごと抜きで、でも愛を込めて「書類」の話をします。紙1枚は、軽くて大した
書類の山に魔法はない。2026年の今、私たちが「やるしかない」現実と、その先の光。
100日ブログ、12日目。今日は、きれいごと抜きで、でも愛を込めて「書類」の話をします。紙1枚は、軽くて大した